いつだったか所属先のDevRelの方から、プロポーザルいっぱい出せた理由とかなにかあるんですか、的な質問をもらった。チーム内でプロポーザル出そうぜ、ていう話をして、レビューしあいながら複数出したらいくつか通過した、と答えた。僕個人としては意識して取り組んだことではなかったのだけども、すごく喜んでもらえて、やってよかったなと思った。もちろん登壇してきたメンバーもイベントを楽しんできたようでほんとによかった。
日本国内だけでも大小さまざまなイベントがある。全部行ってたらきりないけども、現場のエンジニア向けのイベントでも学会でも興味があって、もろもろ都合がつくならどんどん行くのがいいと僕は思う。それで、行ったら発表者に質問して、輪に入るのがいい。でも、僕もそうなんだけど、その輪に入るコミュ力が足りない。そんな時の手段の一つが登壇者になることだと思う。すなわち、プロポーザルを書くことになる。
イベントや学会に行って、周りのレベルの高さに打ちひしがれるかもしれない。でも、それは全然良い。知り合いが増えたり、気になる技術やテーマができたらもうそれで行った価値はあると思ってる。学会は分野によって雰囲気さまざまだとは思うけど、排他的になってても会の存続難しいと思うし、基本は学会でも新参者ウェルカムなんじゃないかな。だから、わからなくても登壇者に声をかけて知り合いになることはイベントや会にとって大歓迎のはず。イベントや学会は楽しむ姿勢を大事に、すなわちお祭りに行く、という捉え方でいいと思ってる。まあ、お祭りといつつワー、キャーいうような場ではないけど、特に学会は。
ちなみに、発表聞いて、半分内容理解できたらいい方なんじゃないかなと僕は個人的に思ってる。学会ならもっとわからなくても不思議ではない。もちろん長らくその分野にいる先生方なら話は違うんだろうけど普通の参加者はそうじゃないかな。
技芸から工学へ(引用 2019年SRE考 - ゆううきブログ)、とゆううきさんが言っていた。僕はなんやかんやソフトウェア工学の分野で博士までとったんだけど、ここで得た知見や経験をどう活かせるんだろうとよく考える(この経験を活かさないと、お世話になった先生方に申し訳ない、という気持ち強い)。で、まさにこの技芸から工学へ、ということへの貢献が現場でソフトウェア開発している身としてすべきことなんだろうなと最近思ってる。具体的なHowとしては、カンファレンスで現場での苦労や工夫を発信しながら、そして工学になるようどこかで体系化や抽象化して多くの方に利用してもらえるよう論文にする、ということを繰り返すことなんだろうな。
書籍 モダン・ソフトウェアエンジニアリングでは、乱立している手法やプラクティスを整理し、これまでのソフトウェアエンジニアリングを再考した。はじめてこの本を読んだとき、なかなかの衝撃を受けた。どう考えても僕がこういった偉業を成すことはないんだけど、このソフトウェアエンジニアリングの再考にいたるまでには本当に多くの方の取り組みがあったと思う。当たり前だけども。LLMの利用によって、改めてソフトウェアエンジニアリングの捉え直しがあるんだろう。そして、それまでにはまだまだ多くの現場での試行錯誤の発信は必要だと考えてる。だって毎日困ってるんだから、まだまだ課題はころがってる。だから、これからも大なり小なり(小が大きいと思う笑)発信は積極的にする所存。それが次の誰かの偉業に貢献でもできたら生きてエンジニアしてた甲斐がある。
ということで、これからもプロポーザルの準備は全力でする。お祭りに行く準備をする。そして実践を通しての経験を抽象化、体系化という形で論文を書きながらより多くの方、コミュニティへの貢献へ繋げたい。繋がったら嬉しい。それが僕がエンジニアしてるうちに少しでもうまくできたらこの仕事してきた甲斐があるんじゃないかしら。技芸の積み重ねから工学へ、そして現場に向き合うエンジニアとして工学も技芸も使いながら日々課題に向き合う。そういう感じでやっていきたい。楽しそう。終わり。
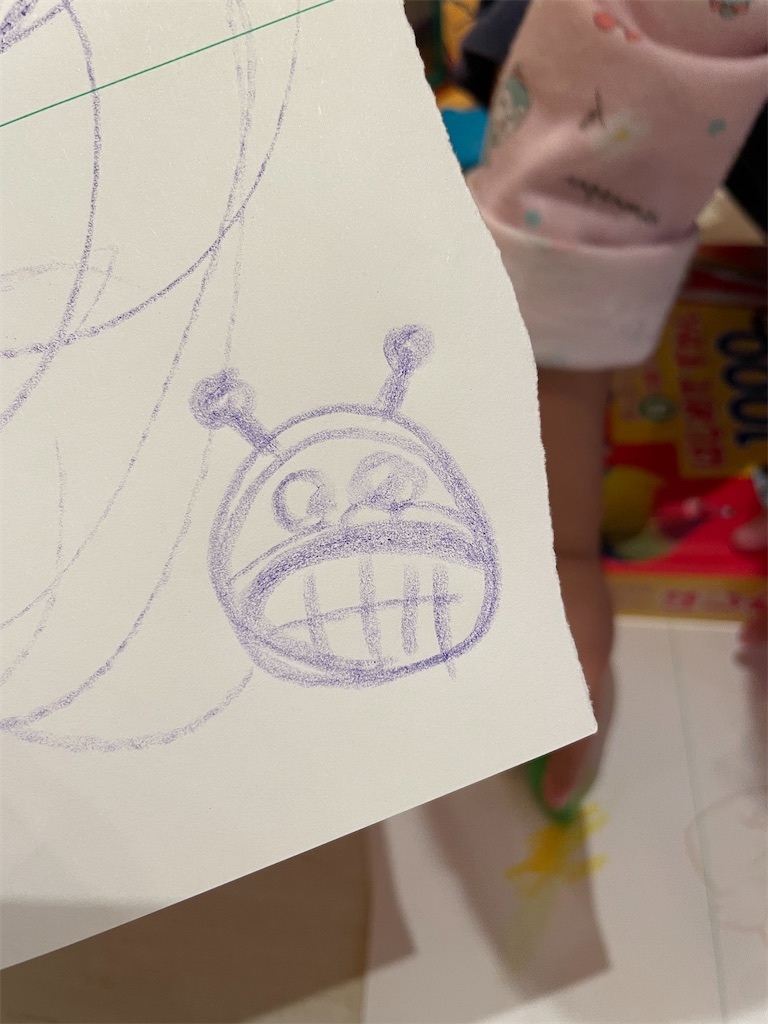
↑これは娘のリクエストで書いた技芸のかけらもないバイキンマン。娘にも、ちがうねー、と言われた。
